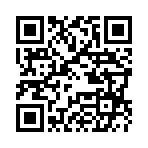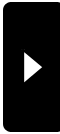2009年12月30日
SOSの猿
伊坂幸太郎の『SOSの猿』は面白かった!
私としては、今年、一番面白かったかも。
ぐいぐい読ませる展開と、
最後に「ああ、なるほど」と思わせてから、
さらに話がドライブしていくところがよかった。
それと、なんというか、「善」とか「意志」をきちんと描いているところ。
今年は個人的にいろいろあって、
あんまり、小説を読む
(架空の世界に入る)モードにならなかったのだけど、
そんな中でも、ちゃんと堪能させてくれる小説でした。
ここ最近の伊坂幸太郎は、ちょっと、当たり外れというか
(いや、違うか、好き嫌いという感じ?)
が分かれるような気もしていたんだけど、
これはかなり当たり。好きでした。
私としては、今年、一番面白かったかも。
ぐいぐい読ませる展開と、
最後に「ああ、なるほど」と思わせてから、
さらに話がドライブしていくところがよかった。
それと、なんというか、「善」とか「意志」をきちんと描いているところ。
今年は個人的にいろいろあって、
あんまり、小説を読む
(架空の世界に入る)モードにならなかったのだけど、
そんな中でも、ちゃんと堪能させてくれる小説でした。
ここ最近の伊坂幸太郎は、ちょっと、当たり外れというか
(いや、違うか、好き嫌いという感じ?)
が分かれるような気もしていたんだけど、
これはかなり当たり。好きでした。
タグ :伊坂幸太郎
2009年12月29日
2009年
今年も終わりますねえ。
そして、今年もさっぱり、こちらのブログは更新できませんでしたm(__)m
携帯などモバイルでの更新ができない
(登録してない)ので……。
PCにゆっくり向かう時間がないので……。
ていうか、複数のブログを管理するのは難しいですね……。
と、弱音ばかりをはいてみました。
もう一個の、携帯写真でぼちぼちとアップしている日常ブログは、
スローペースですが続けております。
せっかく(と言ってもだれに頼まれてるわけでもないけども)
続けているブログなので、
来年はもう少し、なんとかしたいと思っています。
なんか、今年はいろいろとあって、
あんまりゆっくり本読む時間がなかったような気もするなあ……。
今年、思い出せる本を、後ほどアップしようかと思います。
では!
そして、今年もさっぱり、こちらのブログは更新できませんでしたm(__)m
携帯などモバイルでの更新ができない
(登録してない)ので……。
PCにゆっくり向かう時間がないので……。
ていうか、複数のブログを管理するのは難しいですね……。
と、弱音ばかりをはいてみました。
もう一個の、携帯写真でぼちぼちとアップしている日常ブログは、
スローペースですが続けております。
せっかく(と言ってもだれに頼まれてるわけでもないけども)
続けているブログなので、
来年はもう少し、なんとかしたいと思っています。
なんか、今年はいろいろとあって、
あんまりゆっくり本読む時間がなかったような気もするなあ……。
今年、思い出せる本を、後ほどアップしようかと思います。
では!
2009年06月10日
1Q84 BOOK1
1Q84 BOOK1〈4月‐6月〉
村上春樹
新潮社
本体1800円
えー、というわけで「1Q84」。
空前のベストセラーになっているようですね。
発売12日で100万部超えたとか。
すげえ。
出版社に勤めていた経験もあるので
(というか、そういう経験がなくてもたやすく想像できると思いますが)
この数字のものすごさを、しみじみ、かみしめます。
出版不況とか言われている中で、
こういう売れ方ができる作品を日本人の作家が世に出したというのは、
単純に、すばらしいことだ、という気がします。
しかもそれが、この、いろんな示唆とか暗示に富んでいる
村上春樹作品だというのは、
なかなか、かなり、すばらしいことなんではなかろうか。
私はそのくらい、村上春樹という書き手を信頼しているし、
とりあえず、この1巻目まで読んだ時点で、
この世界を100万人が共有してるのかと思うと、
なんか、うれしいような、しかしまあ、奇妙なような、
でもやっぱり、これはいいことだな、という、そんな気がしたんでした。
以下は基本的にネタバレありありの「1Q84 BOOK1」の感想、というか、
個人的、かつランダムな覚書です。
・すごく多重構造な物語だなあ、という感じ。
・主人公二人が、それぞれ三人称で出てくるというのは
村上作品に今までなかったパターンではないだろうか。
・でも、それが読んでいて、気持ちいいリズムになっていて、けっこう快感。
・「多重構造」というのは、特に、「時間」について。
・小説内の時間が、1984年と1Q84年の二重になっている、というのと同時に、
読み手にとって、その1984年が、自分自身が過ごした現実の1984年と、
おそらく無意識に(意識的に、という人もいるだろうけれど)
常に比較される、という二重性。
そして、二人の主人公(青豆、と、天吾)の間でもそれぞれ
似ているけれど、おそらくきっと別な1984年(1Q84年)が展開されている。
・このへんの時間感覚がいったいどう統合されていくかが、2巻目の読みどころ、かも。
・そうそう、多重構造なのは時間だけじゃなく、
この小説の中で、小説が書かれ、その小説がベストセラーになっている、というところ。
ふかえりの小説が売れる、ということと、この村上春樹の新刊が売れているということを
二重の現象に感じる読者はいるはず(ていうか私はそう)だ。
・多重構造、というか、対比構造、でもあるかな。
・それにしても、100万人が読んでいるそうだが、青豆の「きんたま蹴り」のくだりで
思わず顔をしかめたおじさんはいったい何人ぐらいいるんだろうか?
・天吾が小説をリライトしていく描写が、長いインタビューをテープ起こしして
まとめていく作業をしているときの自分の感覚とけっこう似ているような気がした。
・そういうふうに「自分だけがわかっていると思うような感覚」を書くのは
村上春樹の得意とするところだと思う。
・「リトルピープル」はやっぱり「やみくろ」とか「ワタナベノボル」みたいな
得体が知れない極悪なものの代名詞なんだろうか。だろうな。
・ということは、2巻目はそいつらと闘うんだろうな。
・でも、この物語は、青豆さんと天吾くんのラブストーリーとも読める。
・1巻目では、二人のつながりが徐々に解き明かされていくところに
読んでてカタルシスがありました。
・できることなら、青豆さんには、天吾くんと首尾よくめぐりあって、どうか幸せになってほしいなあ。
(なかなかそうはいかないのかもしれなのだろうが)
・これを読み始めて、夜空に月をみつけると、つい、2つないかどうか、まじまじとみてしまう。
そんじゃ、これから、2巻目、読みます!(わくわく)
村上春樹
新潮社
本体1800円
えー、というわけで「1Q84」。
空前のベストセラーになっているようですね。
発売12日で100万部超えたとか。
すげえ。
出版社に勤めていた経験もあるので
(というか、そういう経験がなくてもたやすく想像できると思いますが)
この数字のものすごさを、しみじみ、かみしめます。
出版不況とか言われている中で、
こういう売れ方ができる作品を日本人の作家が世に出したというのは、
単純に、すばらしいことだ、という気がします。
しかもそれが、この、いろんな示唆とか暗示に富んでいる
村上春樹作品だというのは、
なかなか、かなり、すばらしいことなんではなかろうか。
私はそのくらい、村上春樹という書き手を信頼しているし、
とりあえず、この1巻目まで読んだ時点で、
この世界を100万人が共有してるのかと思うと、
なんか、うれしいような、しかしまあ、奇妙なような、
でもやっぱり、これはいいことだな、という、そんな気がしたんでした。
以下は基本的にネタバレありありの「1Q84 BOOK1」の感想、というか、
個人的、かつランダムな覚書です。
・すごく多重構造な物語だなあ、という感じ。
・主人公二人が、それぞれ三人称で出てくるというのは
村上作品に今までなかったパターンではないだろうか。
・でも、それが読んでいて、気持ちいいリズムになっていて、けっこう快感。
・「多重構造」というのは、特に、「時間」について。
・小説内の時間が、1984年と1Q84年の二重になっている、というのと同時に、
読み手にとって、その1984年が、自分自身が過ごした現実の1984年と、
おそらく無意識に(意識的に、という人もいるだろうけれど)
常に比較される、という二重性。
そして、二人の主人公(青豆、と、天吾)の間でもそれぞれ
似ているけれど、おそらくきっと別な1984年(1Q84年)が展開されている。
・このへんの時間感覚がいったいどう統合されていくかが、2巻目の読みどころ、かも。
・そうそう、多重構造なのは時間だけじゃなく、
この小説の中で、小説が書かれ、その小説がベストセラーになっている、というところ。
ふかえりの小説が売れる、ということと、この村上春樹の新刊が売れているということを
二重の現象に感じる読者はいるはず(ていうか私はそう)だ。
・多重構造、というか、対比構造、でもあるかな。
・それにしても、100万人が読んでいるそうだが、青豆の「きんたま蹴り」のくだりで
思わず顔をしかめたおじさんはいったい何人ぐらいいるんだろうか?
・天吾が小説をリライトしていく描写が、長いインタビューをテープ起こしして
まとめていく作業をしているときの自分の感覚とけっこう似ているような気がした。
・そういうふうに「自分だけがわかっていると思うような感覚」を書くのは
村上春樹の得意とするところだと思う。
・「リトルピープル」はやっぱり「やみくろ」とか「ワタナベノボル」みたいな
得体が知れない極悪なものの代名詞なんだろうか。だろうな。
・ということは、2巻目はそいつらと闘うんだろうな。
・でも、この物語は、青豆さんと天吾くんのラブストーリーとも読める。
・1巻目では、二人のつながりが徐々に解き明かされていくところに
読んでてカタルシスがありました。
・できることなら、青豆さんには、天吾くんと首尾よくめぐりあって、どうか幸せになってほしいなあ。
(なかなかそうはいかないのかもしれなのだろうが)
・これを読み始めて、夜空に月をみつけると、つい、2つないかどうか、まじまじとみてしまう。
そんじゃ、これから、2巻目、読みます!(わくわく)
2009年06月10日
マンガアンケート90年代
だいぶ間が空いてしまいましたが、「マンガアンケート」に答えたものの続き。
90年代の巻、です。
***********
●1990年~1999年に刊行されたコミックスの中で、今の読者にオススメしたいマンガ、また、大きな影響を与えたと考えるマンガを5作(順位は不要です)挙げてください。その理由もひと言~100文字程度でお答えください。
作品名 Blue 著者名 山本直樹
理由 「セックス」を通じて、生きることそのものの不確かさとか切なさとか綺麗さとか、刹那な、なんとも言えない「気分」を描き出す山本直樹の傑作短編。90年代不健全図書指定で発禁騒ぎとなったが、(何度か出版社を変えて)無事、単行本は再版されている。
作品名 スラムダンク 著者名 井上雄彦
理由 これはもう、言わずと知れた、90年代の「金字塔」でしょう。何度読み返したことか。時間描写の濃密さ。ストーリーの中での「花道」のめざましい成長度と、井上雄彦の画力の驚異的な進化がシンクロしているところも、この稀有な濃密さのもとになっているのではないだろうか。
作品名 ハッピーマニア 著者名 安野モヨコ
理由 その後の「ちょっと大人向け少女マンガ」ほぼすべてに影響を与えた、エポックメイクな作品。ストーリー(ネーム)ももちろんだが、構図、キャラ、すべてにおいて、「少女マンガ(大人向け)で恋愛を描く」描き方に先鞭をつけた、安野モヨコの才能が凝縮して発揮された作品。
作品名 いじめてくん 著者名 吉田戦車
理由 90年代と言えば吉田戦車。そして、「伝染るんです」よりも「いじめてくん」。
作品名 リバーズエッジ 著者名 岡崎京子
理由 90年代、敏感な表現者ほど、資本主義が花開きすべてを覆い尽くしていく中で、ある種の閉塞感と絶望を描く宿命に立ち向かったのではないか。大いなる才能、岡崎京子はそれを、くっきりとこの作品に刻みつけた。
90年代の巻、です。
***********
●1990年~1999年に刊行されたコミックスの中で、今の読者にオススメしたいマンガ、また、大きな影響を与えたと考えるマンガを5作(順位は不要です)挙げてください。その理由もひと言~100文字程度でお答えください。
作品名 Blue 著者名 山本直樹
理由 「セックス」を通じて、生きることそのものの不確かさとか切なさとか綺麗さとか、刹那な、なんとも言えない「気分」を描き出す山本直樹の傑作短編。90年代不健全図書指定で発禁騒ぎとなったが、(何度か出版社を変えて)無事、単行本は再版されている。
作品名 スラムダンク 著者名 井上雄彦
理由 これはもう、言わずと知れた、90年代の「金字塔」でしょう。何度読み返したことか。時間描写の濃密さ。ストーリーの中での「花道」のめざましい成長度と、井上雄彦の画力の驚異的な進化がシンクロしているところも、この稀有な濃密さのもとになっているのではないだろうか。
作品名 ハッピーマニア 著者名 安野モヨコ
理由 その後の「ちょっと大人向け少女マンガ」ほぼすべてに影響を与えた、エポックメイクな作品。ストーリー(ネーム)ももちろんだが、構図、キャラ、すべてにおいて、「少女マンガ(大人向け)で恋愛を描く」描き方に先鞭をつけた、安野モヨコの才能が凝縮して発揮された作品。
作品名 いじめてくん 著者名 吉田戦車
理由 90年代と言えば吉田戦車。そして、「伝染るんです」よりも「いじめてくん」。
作品名 リバーズエッジ 著者名 岡崎京子
理由 90年代、敏感な表現者ほど、資本主義が花開きすべてを覆い尽くしていく中で、ある種の閉塞感と絶望を描く宿命に立ち向かったのではないか。大いなる才能、岡崎京子はそれを、くっきりとこの作品に刻みつけた。
2009年05月02日
マンガアンケート80年代
承前。
というわけで80年代も。
ちなみに、私は1966年生まれなので、
80年代というと、14歳から23歳という、
多感、かつ、自分でお金を出してコミックスも買える、という、
マンガどっぷりな年代でしたね。
***********
●1980年~1989年に刊行されたコミックスの中で、今の読者にオススメしたいマンガ、また、大きな影響を与えたと考えるマンガを5作(順位は不要です)挙げてください。その理由もひと言~100文字程度でお答えください。
作品名 草迷宮・草空間(あるいは、「星の時計のリデル」) 著者名 内田善美
理由 内田善美のマンガの驚くべき繊細さは、80年代の一つの「事件」と言ってもいいくらい、表現として完成度の高いものだったと思う。「詩情豊かな」という表現が、緻密な絵とネームにあいまってこれほどしっくりとくる作家を他には知らない。再版を切に願う。
作品名 物陰に足拍子 著者名 内田春菊
理由 内田春菊の代表作にして傑作。マンガが単なる娯楽表現ではなくて、閉塞した状況の中で、悲鳴を上げる「個」のための表現であることを知らしめた作品。その痛々しい切実さには今でも胸がつまる。
作品名 永遠の野原 著者名 逢坂みえこ
理由 思春期の時代をまっすぐに、しかし、切実に、丁寧に描いた、すがすがしい傑作。思い悩む時にはいつも読み返したくなるような、やさしい強さに満ちている。
作品名 ストップ!!ひばりくん! 著者名 江口寿史
理由「80年代」を象徴する作品。ギャグのスピード感、リズム感、「ひばりくん」のありえないくらいの可愛さ……その全部が「あの時代」に「江口寿史」でないと生み出せないものだった。
作品名 風呂上がりの夜空に 著者名 小林じんこ
理由 RCサクセションの名曲とともに、いつも心に蘇る、自分にとっての「青春」マンガ。「青春」は甘酸っぱく、バカバカしい、そして、「世間には悪意というものがある」という真実と、「それと同じくらい、善意と友情もある」という希望も教えてくれた作品。
************
80年代は好きなマンガがありすぎて、絞るのに苦労した……。
最後は、自分が好きで、なおかつ、今も人にすすめられる、という観点と、他でも票が入りそうなものはまあいいか、という感じで絞ったんでした。
「日出処の天子」(山岸涼子)はまぎれもない名作で、ものすごく入れたかったが、内田善美にゆずった、という感じ。
リアルタイム信者としてはくらもちふさこも入れたかったなあ……。「東京のカサノバ」とか「A-Girl」とか。
しかし、くらもちふさこは名小品が多すぎて、票が入れにくい、というのもある。
80年代といえば、岡崎京子初期作品も忘れ難い。89年にいっぱい単行本が出てた気が。
「ぶ~け」が創刊されたのが70年代末ごろだったと、記憶している。
ビッグコミックスピリッツとか、ヤンマガが創刊されたのも80年頭ごろ。
青年誌が台頭してきた時期でもあります。
私は、「ぶ~け」読者だったもんで、アンケート内でも、「ぶ~け」作品2作入れてます。
(内田善美と逢坂みえこ)
ほんとは、清原なつのも、吉野朔美も入れたかった!!
というか、ふと年代を追ってみて今気づいたんだけど、
読み手として、私の年代が、ちょうど、マンガを読む世代として、
マーケットを広げてきたのかもしれない。
「りぼん」や「なかよし」の少女マンガから、少し大人になっても読める
「ぶ~け」や「ヤングユー」などの大人向け少女漫画誌の創刊へ。
(それから、やや過激なレディコミブームへ。)
「ジャンプ」「サンデー」「マガジン」等の少年誌から
「ヤンサン」「ヤンマガ」「ヤンジャン」「スピリッツ」と
大学生やサラリーマンが読むマンガ誌の創刊へ。
そういうマンガマーケットの広がりが顕著だったのが、
私が10代後半から20歳になるころだったような気がする……。
バブルが始まるころで景気がよかったということもあるんだろうけど、
マンガが「文化」であり「商品」として認知され、爆発的に広まっていく様
(と同時に、オタク的な深みや、ブンガク的な深みを得ていく様)を
リアルタイムで経験できたのは、すごく面白かった、
と今にして思うのであります。
マンガ読むの、毎日、楽しかったなあ……。
(今も楽しいけど。)
ミもフタもないつぶやきでどーもスイマセン(^^ゞ
というわけで80年代も。
ちなみに、私は1966年生まれなので、
80年代というと、14歳から23歳という、
多感、かつ、自分でお金を出してコミックスも買える、という、
マンガどっぷりな年代でしたね。
***********
●1980年~1989年に刊行されたコミックスの中で、今の読者にオススメしたいマンガ、また、大きな影響を与えたと考えるマンガを5作(順位は不要です)挙げてください。その理由もひと言~100文字程度でお答えください。
作品名 草迷宮・草空間(あるいは、「星の時計のリデル」) 著者名 内田善美
理由 内田善美のマンガの驚くべき繊細さは、80年代の一つの「事件」と言ってもいいくらい、表現として完成度の高いものだったと思う。「詩情豊かな」という表現が、緻密な絵とネームにあいまってこれほどしっくりとくる作家を他には知らない。再版を切に願う。
作品名 物陰に足拍子 著者名 内田春菊
理由 内田春菊の代表作にして傑作。マンガが単なる娯楽表現ではなくて、閉塞した状況の中で、悲鳴を上げる「個」のための表現であることを知らしめた作品。その痛々しい切実さには今でも胸がつまる。
作品名 永遠の野原 著者名 逢坂みえこ
理由 思春期の時代をまっすぐに、しかし、切実に、丁寧に描いた、すがすがしい傑作。思い悩む時にはいつも読み返したくなるような、やさしい強さに満ちている。
作品名 ストップ!!ひばりくん! 著者名 江口寿史
理由「80年代」を象徴する作品。ギャグのスピード感、リズム感、「ひばりくん」のありえないくらいの可愛さ……その全部が「あの時代」に「江口寿史」でないと生み出せないものだった。
作品名 風呂上がりの夜空に 著者名 小林じんこ
理由 RCサクセションの名曲とともに、いつも心に蘇る、自分にとっての「青春」マンガ。「青春」は甘酸っぱく、バカバカしい、そして、「世間には悪意というものがある」という真実と、「それと同じくらい、善意と友情もある」という希望も教えてくれた作品。
************
80年代は好きなマンガがありすぎて、絞るのに苦労した……。
最後は、自分が好きで、なおかつ、今も人にすすめられる、という観点と、他でも票が入りそうなものはまあいいか、という感じで絞ったんでした。
「日出処の天子」(山岸涼子)はまぎれもない名作で、ものすごく入れたかったが、内田善美にゆずった、という感じ。
リアルタイム信者としてはくらもちふさこも入れたかったなあ……。「東京のカサノバ」とか「A-Girl」とか。
しかし、くらもちふさこは名小品が多すぎて、票が入れにくい、というのもある。
80年代といえば、岡崎京子初期作品も忘れ難い。89年にいっぱい単行本が出てた気が。
「ぶ~け」が創刊されたのが70年代末ごろだったと、記憶している。
ビッグコミックスピリッツとか、ヤンマガが創刊されたのも80年頭ごろ。
青年誌が台頭してきた時期でもあります。
私は、「ぶ~け」読者だったもんで、アンケート内でも、「ぶ~け」作品2作入れてます。
(内田善美と逢坂みえこ)
ほんとは、清原なつのも、吉野朔美も入れたかった!!
というか、ふと年代を追ってみて今気づいたんだけど、
読み手として、私の年代が、ちょうど、マンガを読む世代として、
マーケットを広げてきたのかもしれない。
「りぼん」や「なかよし」の少女マンガから、少し大人になっても読める
「ぶ~け」や「ヤングユー」などの大人向け少女漫画誌の創刊へ。
(それから、やや過激なレディコミブームへ。)
「ジャンプ」「サンデー」「マガジン」等の少年誌から
「ヤンサン」「ヤンマガ」「ヤンジャン」「スピリッツ」と
大学生やサラリーマンが読むマンガ誌の創刊へ。
そういうマンガマーケットの広がりが顕著だったのが、
私が10代後半から20歳になるころだったような気がする……。
バブルが始まるころで景気がよかったということもあるんだろうけど、
マンガが「文化」であり「商品」として認知され、爆発的に広まっていく様
(と同時に、オタク的な深みや、ブンガク的な深みを得ていく様)を
リアルタイムで経験できたのは、すごく面白かった、
と今にして思うのであります。
マンガ読むの、毎日、楽しかったなあ……。
(今も楽しいけど。)
ミもフタもないつぶやきでどーもスイマセン(^^ゞ
2009年05月02日
マンガアンケート70年代
先日、60年代ぶんのみ掲載していた、ダヴィンチのマンガアンケート。
70年代の作品とコメント。
***********
●1970年~1979年に刊行されたコミックスの中で、今の読者にオススメしたいマンガ、また、大きな影響を与えたと考えるマンガを5作(順位は不要)挙げてください。その理由も。
作品名 はみだしっ子 著者名 三原順
理由 文学性の高い70年代少女マンガの傑作の中でも、独特の立ち位置を持つマンガ。それぞれ親に捨てられた過去を持つ4人の少年たちの深い絆と葛藤が、繊細かつ骨太に綴られる。愛すべきキャラクターそれぞれも描き方も絶妙。個人的に、人生観を変えられたマンガ。
作品名 バナナブレッドのプディング 著者名 大島弓子
理由 大島作品、「綿の国星」とどちらを取るかで悩んだあげくに、こちらに軍配。少女ならでは、いや、人間ならではの切ないどうどうめぐりを切り取る手腕の鮮やかさ。ラストの奇跡的な美しさにも脱帽。
作品名 デザイナー 著者名 一条ゆかり
理由 一条ゆかりの初期代表作にして、原点、とも言うべき作品。絵のゴージャスさ、設定の深さ、女性と仕事と恋愛(プラス親子関係)、という、少女マンガから現代に発展したレディースコミックのエッセンスのあらゆる意味で原点。
作品名 ガラスの仮面 著者名 美内すずえ
理由 自分自身、立ち読みで、あまりにも棒立ちで真剣に読み過ぎて足がしびれて動けなくなった……というマンガの中のエピソードとかぶるような経験をするほど、熱中して読んだマンガ。「北島マヤになる!」と思った少女は一体何十万人いたことだろう……。未だに連載継続中というのもすごい。
作品名 おれは鉄平 著者名 ちばてつや
理由 70年代少年マンガの中でも、鉄平の野生児キャラは際立っていた。マンガでしかありえないようなのに、とてもリアルで魅力的。個人的には、小学生のころ読んでいた当時「あしたのジョー」と同じ人が描いたとは思えない……と感じたのも印象的。
**********
70年代は「ポーの一族」萩尾望都や、「ベルサイユのばら」池田理代子、それから、田淵由美子、陸奥A子、太刀掛秀子らの往年の「りぼん」おとめちっくマンガなどなど、入れたいものが他にもいろいろあって悩んだんだが、「今の読者にオススメしたい」「影響をあたえた」という観点とバランスから、上記5作に。
個人的記憶としても、作品の質としても、70年代って、少女マンガ黄金時代という気がするなあ。
70年代の作品とコメント。
***********
●1970年~1979年に刊行されたコミックスの中で、今の読者にオススメしたいマンガ、また、大きな影響を与えたと考えるマンガを5作(順位は不要)挙げてください。その理由も。
作品名 はみだしっ子 著者名 三原順
理由 文学性の高い70年代少女マンガの傑作の中でも、独特の立ち位置を持つマンガ。それぞれ親に捨てられた過去を持つ4人の少年たちの深い絆と葛藤が、繊細かつ骨太に綴られる。愛すべきキャラクターそれぞれも描き方も絶妙。個人的に、人生観を変えられたマンガ。
作品名 バナナブレッドのプディング 著者名 大島弓子
理由 大島作品、「綿の国星」とどちらを取るかで悩んだあげくに、こちらに軍配。少女ならでは、いや、人間ならではの切ないどうどうめぐりを切り取る手腕の鮮やかさ。ラストの奇跡的な美しさにも脱帽。
作品名 デザイナー 著者名 一条ゆかり
理由 一条ゆかりの初期代表作にして、原点、とも言うべき作品。絵のゴージャスさ、設定の深さ、女性と仕事と恋愛(プラス親子関係)、という、少女マンガから現代に発展したレディースコミックのエッセンスのあらゆる意味で原点。
作品名 ガラスの仮面 著者名 美内すずえ
理由 自分自身、立ち読みで、あまりにも棒立ちで真剣に読み過ぎて足がしびれて動けなくなった……というマンガの中のエピソードとかぶるような経験をするほど、熱中して読んだマンガ。「北島マヤになる!」と思った少女は一体何十万人いたことだろう……。未だに連載継続中というのもすごい。
作品名 おれは鉄平 著者名 ちばてつや
理由 70年代少年マンガの中でも、鉄平の野生児キャラは際立っていた。マンガでしかありえないようなのに、とてもリアルで魅力的。個人的には、小学生のころ読んでいた当時「あしたのジョー」と同じ人が描いたとは思えない……と感じたのも印象的。
**********
70年代は「ポーの一族」萩尾望都や、「ベルサイユのばら」池田理代子、それから、田淵由美子、陸奥A子、太刀掛秀子らの往年の「りぼん」おとめちっくマンガなどなど、入れたいものが他にもいろいろあって悩んだんだが、「今の読者にオススメしたい」「影響をあたえた」という観点とバランスから、上記5作に。
個人的記憶としても、作品の質としても、70年代って、少女マンガ黄金時代という気がするなあ。
2009年04月29日
本日購入した本
万城目学 「ホルモー六景」 角川書店 本体1300円
勝間和代 「断る力」 文春新書 本体900円
原作・大場つぐみ 漫画:小畑健 「BAKUMAN」② 本体400円
節操が感じられないというか、なんというか、
本屋で小一時間うろうろして、結局この3冊をレジに出したとき、
なんか、恥ずかしかったです、私。
「ホルモー六景」は、映画化で話題の「鴨川ホルモー」を文庫で読んだら
期待以上に面白かったので買った続編。
勝間和代は、同世代の友人(女性)に、
「読んでみるとけっこう役に立つよ」と言われ、
あまりに売れてるようで、あと、この手の自己啓発、自己改革モノには
食指が動かないんだけど、とにかく、一度読んでみるか、と思い、
たまたま手にしたみた一冊。未読です。
読んだら感想書く…………かも。
「バクマン」は少年ジャンプ連載中。ジャンプの中で現在最も注目しているマンガ。
というか、少年誌のマンガでコミックスまで買って読む作品は久々。
「青春漫画執筆活劇」というコピーがついてます。
内容はそのまんまです。
マンガ(マンガ家)を描くマンガは「まんが道」をはじめ各種名作があるけど、
その最新型。
これを少年誌でやるっていうのがすごい……と思う。
面白いです。
今、「ホルモー六景」途中まで読んでますが、
やっぱりかなり面白い。
「三景」の章を読んだら、これをすごく聴きたくなって
検索したらyoutubeで出てきた。
(便利な世の中や……)
名曲だなあ。
私も歌詞全部覚えてた(笑)。
勝間和代 「断る力」 文春新書 本体900円
原作・大場つぐみ 漫画:小畑健 「BAKUMAN」② 本体400円
節操が感じられないというか、なんというか、
本屋で小一時間うろうろして、結局この3冊をレジに出したとき、
なんか、恥ずかしかったです、私。
「ホルモー六景」は、映画化で話題の「鴨川ホルモー」を文庫で読んだら
期待以上に面白かったので買った続編。
勝間和代は、同世代の友人(女性)に、
「読んでみるとけっこう役に立つよ」と言われ、
あまりに売れてるようで、あと、この手の自己啓発、自己改革モノには
食指が動かないんだけど、とにかく、一度読んでみるか、と思い、
たまたま手にしたみた一冊。未読です。
読んだら感想書く…………かも。
「バクマン」は少年ジャンプ連載中。ジャンプの中で現在最も注目しているマンガ。
というか、少年誌のマンガでコミックスまで買って読む作品は久々。
「青春漫画執筆活劇」というコピーがついてます。
内容はそのまんまです。
マンガ(マンガ家)を描くマンガは「まんが道」をはじめ各種名作があるけど、
その最新型。
これを少年誌でやるっていうのがすごい……と思う。
面白いです。
今、「ホルモー六景」途中まで読んでますが、
やっぱりかなり面白い。
「三景」の章を読んだら、これをすごく聴きたくなって
検索したらyoutubeで出てきた。
(便利な世の中や……)
名曲だなあ。
私も歌詞全部覚えてた(笑)。
2009年04月23日
マンガアンケート60年代
そういえば。
昔、マンガにかかわる編集を手がけていたり、
マンガ家インタビューなどをしていて、
宝島社の「このマンガがすごい」シリーズでお仕事させていただいたりした縁もあって、
先日、ダ・ヴィンチという雑誌から15周年記念号(2009年5月号)の
「殿堂入りプラチナマンガランキング」という特集用の
アンケートを依頼されたんでした。
そのアンケート結果の集計は、
現在発売中の雑誌を見ていただくとして。
ランキングとはかなり違ったものになったんですが、
アンケート用に、60年代、70年代、80年代、90年代、00年代各5冊を挙げて、
理由コメントを考える、というのは、
なかなか難しくもありましたが、個人的にも面白い作業でした。
てなわけで、その時のアンケートに自分が記した作品とコメントをここに記しておきます。
********
●1960年~1969年に刊行された全てのコミックスの中で、今の読者にオススメしたいマンガ、また、大きな影響を与えたと考えるマンガ5作
作品名 紅い花 著者名 つげ義春
理由 60年代の抒情、と言って何よりも思い浮かぶつげ義春の名短編。映画、演劇、音楽、文学など、日本のさまざまな表現にマンガが大きな影響を与えるひとつの先駆けとなった作品。モノクロなのに、目に染みいるように鮮やか。
作品名 男一匹ガキ大将 著者名 本宮ひろ志
理由 個人的に、物心ついて、一番初めに熱中した少年マンガ。高度経済成長時代ならではのスケールの成り上がりストーリーがド迫力で展開される様には否が応でもひきこまれる。あの時代ならではの少年マンガの筆圧、迫力を堪能できる傑作。
作品名 あしたのジョー 著者名 高森朝雄・ちばてつや
理由 (70年代のリストのほうに入っていましたが、連載時期(1967年より連載開始)を考えると、最初の単行本1巻目が出たのは60年代ではないかと思い、こちらに入れました。)
言わずと知れたスポーツ漫画の金字塔。戦いの臨場感、力石をはじめ数々のライバルのキャラクターなど、忘れられない部分があまりに多い名作中の名作。世代的にはアニメのほうの印象が強いので、マンガで読んでもジョーの声はあおい輝彦で読んでしまう……。
作品名 サイボーグ009 著者名 石ノ森章太郎
理由 こちらも、世代的にはアニメで入って、後追いでマンガを読んだ……というタイプの作品。(たぶん、各年代ごとにそうした出会い方のマンガ作品は多いことでしょうが。)数ある石ノ森作品の中でも各サイボーグのキャラクターの造形、設定や世界観の哲学的な深さが際立つ難解さを持ちつつ、「とにかくカッコいい!」と少年少女の胸をときめかせることにも成功した稀有な作品。
作品名 サザエさん 著者名 長谷川町子
理由 (厳密には1950年代から新聞連載で、おそらく最初の単行本化も60年より前でしょうが、「60年代」にリアルタイムに原作を読んだ記憶が鮮明な作品なので……。)アニメの毒抜きな感じとは違って、原作は4コマ漫画としての面白さ、皮肉も含めたウィットに富んだ面白さがあったと記憶している。昭和40年代、必ずほとんどの家庭に単行本が1冊あって、実は「子どもが初めて出会う、大人の世界(世間)を知るマンガ」になっていた気がする。
*******
70年代以降はまた後日。
昔、マンガにかかわる編集を手がけていたり、
マンガ家インタビューなどをしていて、
宝島社の「このマンガがすごい」シリーズでお仕事させていただいたりした縁もあって、
先日、ダ・ヴィンチという雑誌から15周年記念号(2009年5月号)の
「殿堂入りプラチナマンガランキング」という特集用の
アンケートを依頼されたんでした。
そのアンケート結果の集計は、
現在発売中の雑誌を見ていただくとして。
ランキングとはかなり違ったものになったんですが、
アンケート用に、60年代、70年代、80年代、90年代、00年代各5冊を挙げて、
理由コメントを考える、というのは、
なかなか難しくもありましたが、個人的にも面白い作業でした。
てなわけで、その時のアンケートに自分が記した作品とコメントをここに記しておきます。
********
●1960年~1969年に刊行された全てのコミックスの中で、今の読者にオススメしたいマンガ、また、大きな影響を与えたと考えるマンガ5作
作品名 紅い花 著者名 つげ義春
理由 60年代の抒情、と言って何よりも思い浮かぶつげ義春の名短編。映画、演劇、音楽、文学など、日本のさまざまな表現にマンガが大きな影響を与えるひとつの先駆けとなった作品。モノクロなのに、目に染みいるように鮮やか。
作品名 男一匹ガキ大将 著者名 本宮ひろ志
理由 個人的に、物心ついて、一番初めに熱中した少年マンガ。高度経済成長時代ならではのスケールの成り上がりストーリーがド迫力で展開される様には否が応でもひきこまれる。あの時代ならではの少年マンガの筆圧、迫力を堪能できる傑作。
作品名 あしたのジョー 著者名 高森朝雄・ちばてつや
理由 (70年代のリストのほうに入っていましたが、連載時期(1967年より連載開始)を考えると、最初の単行本1巻目が出たのは60年代ではないかと思い、こちらに入れました。)
言わずと知れたスポーツ漫画の金字塔。戦いの臨場感、力石をはじめ数々のライバルのキャラクターなど、忘れられない部分があまりに多い名作中の名作。世代的にはアニメのほうの印象が強いので、マンガで読んでもジョーの声はあおい輝彦で読んでしまう……。
作品名 サイボーグ009 著者名 石ノ森章太郎
理由 こちらも、世代的にはアニメで入って、後追いでマンガを読んだ……というタイプの作品。(たぶん、各年代ごとにそうした出会い方のマンガ作品は多いことでしょうが。)数ある石ノ森作品の中でも各サイボーグのキャラクターの造形、設定や世界観の哲学的な深さが際立つ難解さを持ちつつ、「とにかくカッコいい!」と少年少女の胸をときめかせることにも成功した稀有な作品。
作品名 サザエさん 著者名 長谷川町子
理由 (厳密には1950年代から新聞連載で、おそらく最初の単行本化も60年より前でしょうが、「60年代」にリアルタイムに原作を読んだ記憶が鮮明な作品なので……。)アニメの毒抜きな感じとは違って、原作は4コマ漫画としての面白さ、皮肉も含めたウィットに富んだ面白さがあったと記憶している。昭和40年代、必ずほとんどの家庭に単行本が1冊あって、実は「子どもが初めて出会う、大人の世界(世間)を知るマンガ」になっていた気がする。
*******
70年代以降はまた後日。
2009年04月22日
映画「シャイン・ア・ライト」
更新してないにもほどがあるっつーの。
という状況ですが。
読んだ本はいろいろあるんですけどね。
更新するとか有言不実行でしたが。
やります。
もうちょっと。
で、本の話ではないんですが。
観ました。
ストーンズの、というか、スコセッシの
「シャイン・ア・ライト」。
内地ではとっくの昔にやっていたんでしょうが、
沖縄ではやっと最近になってから先週まで、
桜坂劇場でやってたわけです。
私はストーンズ好きなので。
というか、何故かいろいろ縁もタイミングもあって、
これまですべての来日ツアーをどこかで何かしらの形で見れている、
という果報者なので、
そして、スコセッシの映画はけっこう好きだし、「ラスト・ワルツ」も好きなので、
映画完成の時点から非常に期待して楽しみにしていた映画でした。
んで、念願かなって、よおおやく、観ることができたんですが。
さすが、ストーンズ。
つうか、さすが、ミック・ジャガー。
そして、さすが、スコセッシ。
……としみじみ思える映画だったんですが、
正直、
期待が大きすぎたってのもあるかもしれないが、
ちょっと、なんだか、何か、足りなかった。
アップが多すぎるというか。
臨場感のための臨場感、という感じがぬぐえず。
映画にするなら、それこそ、ストーンズ側の最初のアイデアだったという
リオで巨大な会場でやるやつを撮ったらよかったんじゃないかなーと。
私は、それが見たかった。
まあ、私はキース派なので、
あくまでミック中心の濃いい映像に
途中でちょっとばかり飽きた、というのもある。
あと、瑣末なことかもしれんが、
この、プレミアム中のプレミアムなライブの最中、
ステージ目の前の客席にいるやつが
ニヤニヤしながら携帯で写真撮ってる様が
客席ショットで何度も写っていて、
非常に目ざわりだった。
なんなんだ、あれ(怒)。
しかしまあ、演奏はとんでもなくすばらしく、サントラ買おうかなー、
と帰ってきてからあらためて思う映画でした。
それと、若いころのストーンズの記録映像が挟み込まれていて、
これが、絶妙。
それにしても。
若い時のキース、かっけえええええ!
私にとって、あの、若い時(20代はじめぐらいなのか)の
キースのルックスは理想中の理想、ツボの中のツボ(なんじゃそら)だと
再認識いたしました。
(すみません。ミーハーのたわごとで。)
しかし、演奏も映像も異様にかっこいいので
もういっかいDVDで観てみる価値はあるかと思います。
という状況ですが。
読んだ本はいろいろあるんですけどね。
更新するとか有言不実行でしたが。
やります。
もうちょっと。
で、本の話ではないんですが。
観ました。
ストーンズの、というか、スコセッシの
「シャイン・ア・ライト」。
内地ではとっくの昔にやっていたんでしょうが、
沖縄ではやっと最近になってから先週まで、
桜坂劇場でやってたわけです。
私はストーンズ好きなので。
というか、何故かいろいろ縁もタイミングもあって、
これまですべての来日ツアーをどこかで何かしらの形で見れている、
という果報者なので、
そして、スコセッシの映画はけっこう好きだし、「ラスト・ワルツ」も好きなので、
映画完成の時点から非常に期待して楽しみにしていた映画でした。
んで、念願かなって、よおおやく、観ることができたんですが。
さすが、ストーンズ。
つうか、さすが、ミック・ジャガー。
そして、さすが、スコセッシ。
……としみじみ思える映画だったんですが、
正直、
期待が大きすぎたってのもあるかもしれないが、
ちょっと、なんだか、何か、足りなかった。
アップが多すぎるというか。
臨場感のための臨場感、という感じがぬぐえず。
映画にするなら、それこそ、ストーンズ側の最初のアイデアだったという
リオで巨大な会場でやるやつを撮ったらよかったんじゃないかなーと。
私は、それが見たかった。
まあ、私はキース派なので、
あくまでミック中心の濃いい映像に
途中でちょっとばかり飽きた、というのもある。
あと、瑣末なことかもしれんが、
この、プレミアム中のプレミアムなライブの最中、
ステージ目の前の客席にいるやつが
ニヤニヤしながら携帯で写真撮ってる様が
客席ショットで何度も写っていて、
非常に目ざわりだった。
なんなんだ、あれ(怒)。
しかしまあ、演奏はとんでもなくすばらしく、サントラ買おうかなー、
と帰ってきてからあらためて思う映画でした。
それと、若いころのストーンズの記録映像が挟み込まれていて、
これが、絶妙。
それにしても。
若い時のキース、かっけえええええ!
私にとって、あの、若い時(20代はじめぐらいなのか)の
キースのルックスは理想中の理想、ツボの中のツボ(なんじゃそら)だと
再認識いたしました。
(すみません。ミーハーのたわごとで。)
しかし、演奏も映像も異様にかっこいいので
もういっかいDVDで観てみる価値はあるかと思います。
2008年12月26日
更新してませんでしたー!
9月に「リニューアル」だとか言って以来、
結局更新してませんでした。
もう年末になってしまいました。
とりあえず、年を越す前に、今年後半読んだもので、
今、机のまわりにあるものを防備録的に。
・「子宮会議」洞口依子(小学館)
子宮頸がんの闘病をつづった、女優・洞口依子の手記。
切々と、でもどこか飄々と、自分の世界を持つ女優さんならではの価値観や自分観もにじみ出ている作品。今年、子宮頸がん検査についての取材もしたので、トークショウに行く機会もあったのだけど、そのときの自作の朗読がすごかった。今年は、「がん」についてはいろいろな形で考える機会がありました。機会があった、というだけで、まだ自分のなかで考えはまとまってはいないけれど。来年もひきつづき考えていくことになると思う。
・「図書館戦争」有川浩(メディアワークス)
K春さんから借りた物。有川浩って名前は知ってたけどちゃんと読んだのは初。思ってた以上に面白く読めた。続編読みたい~。
・「街場の教育論」内田樹(ミシマ社)
今年後半はとにかく内田センセイにハマった。
中でもこれは名著!というべき、とても腑に落ちまくる、問題意識をかきたてられる書でした。自分自身を含め「学ぶ」ということを再認識する、というか、読んでいるだけでも自分内OSが更新されそうな気がする良書、と思います。
・「身体の言い分」内田樹 池上六朗(毎日新聞社)
内田センセイシリーズ。これは、言ってる内容はすごく面白かったけど、中盤ちょっと読みにくかったような気が。対談形式のものって、編集者のセンスなのか、話者間の間で共有されていることをどういう風に読み手が共有できるか、という部分で、あたりはずれが大きいような気がする。今度再読してみようかな。
時間もないので、今日はこれだけ。
結局更新してませんでした。
もう年末になってしまいました。
とりあえず、年を越す前に、今年後半読んだもので、
今、机のまわりにあるものを防備録的に。
・「子宮会議」洞口依子(小学館)
子宮頸がんの闘病をつづった、女優・洞口依子の手記。
切々と、でもどこか飄々と、自分の世界を持つ女優さんならではの価値観や自分観もにじみ出ている作品。今年、子宮頸がん検査についての取材もしたので、トークショウに行く機会もあったのだけど、そのときの自作の朗読がすごかった。今年は、「がん」についてはいろいろな形で考える機会がありました。機会があった、というだけで、まだ自分のなかで考えはまとまってはいないけれど。来年もひきつづき考えていくことになると思う。
・「図書館戦争」有川浩(メディアワークス)
K春さんから借りた物。有川浩って名前は知ってたけどちゃんと読んだのは初。思ってた以上に面白く読めた。続編読みたい~。
・「街場の教育論」内田樹(ミシマ社)
今年後半はとにかく内田センセイにハマった。
中でもこれは名著!というべき、とても腑に落ちまくる、問題意識をかきたてられる書でした。自分自身を含め「学ぶ」ということを再認識する、というか、読んでいるだけでも自分内OSが更新されそうな気がする良書、と思います。
・「身体の言い分」内田樹 池上六朗(毎日新聞社)
内田センセイシリーズ。これは、言ってる内容はすごく面白かったけど、中盤ちょっと読みにくかったような気が。対談形式のものって、編集者のセンスなのか、話者間の間で共有されていることをどういう風に読み手が共有できるか、という部分で、あたりはずれが大きいような気がする。今度再読してみようかな。
時間もないので、今日はこれだけ。
Posted by ながみねようこ at
17:30
│Comments(2)
2008年09月10日
リニューアル。
あー、もう、ぜんぜん更新していませんでした。
読書記録の付け方に問題があったのかなあ。
どうせなら、出版社とか値段とかも入れよう、としたのが間違いかも。
単なる自分の備忘録なんだから、
タイトル、作者名、作品の印象、など、
シンプルな記述にしたほうがいいのでは、
……と今更ながら思いました。
というわけでリニューアル。
ブログのリニューアルって実に簡単にできていいな。
雑誌のリニューアルではこうはいきません(余談)。
とりあえず、自分でも何を書いたのか(読んだのか)
わかりやすいように、タイトル+作者名を入れて、
あとは簡単なメモ、
たまに、その時々に考えたとりとめのないことなども書いてみようかなと。
どなたか存じませんが、読んでいただいている方、
どうもありがとうございます。
これからもちっと、更新をこころがけますので、
お暇なときにでもまた寄ってっていただけるとありがたいです。
では。
読書記録の付け方に問題があったのかなあ。
どうせなら、出版社とか値段とかも入れよう、としたのが間違いかも。
単なる自分の備忘録なんだから、
タイトル、作者名、作品の印象、など、
シンプルな記述にしたほうがいいのでは、
……と今更ながら思いました。
というわけでリニューアル。
ブログのリニューアルって実に簡単にできていいな。
雑誌のリニューアルではこうはいきません(余談)。
とりあえず、自分でも何を書いたのか(読んだのか)
わかりやすいように、タイトル+作者名を入れて、
あとは簡単なメモ、
たまに、その時々に考えたとりとめのないことなども書いてみようかなと。
どなたか存じませんが、読んでいただいている方、
どうもありがとうございます。
これからもちっと、更新をこころがけますので、
お暇なときにでもまた寄ってっていただけるとありがたいです。
では。
2008年05月25日
かむろば村へ①、②
かむろば村へ ①、②
いがらしみきお
小学館 本体819円+税
あの、「ぼのぼの」の、というか、絶妙な筆致とシュールなギャグの大家、
いがらしみきおの最新連載。
これがビックコミックに連載されてるとは知らなかった~。
(現在も連載中。)
銀行勤めから「金」恐怖症になって、山の中の村に移住してきた
ダメ~な感じの勘違い男を主人公にして、
農村という名の小宇宙で繰り広げられるスラップスティック。
ロハスとかスローライフとか言うのとはぜんぜん違う地平で、
都会を出て農村で暮らすとか、お金を使わず暮らすとか、
そういうことにどういう意味と手触りがあるのか。
そもそも、人が生きる、暮らすことにどういう意味があるのか。
ありえないようなシュールな村なのに、
どこかの地方にほんとうにありそうな、
すごく「場」としての力を持つ「かむろば村」でもって、
そうしたことをいろいろ深ーく感じさせる作品です。
非常に面白いです。
ああ、早く続きが読みたい。
いがらしみきお
小学館 本体819円+税
あの、「ぼのぼの」の、というか、絶妙な筆致とシュールなギャグの大家、
いがらしみきおの最新連載。
これがビックコミックに連載されてるとは知らなかった~。
(現在も連載中。)
銀行勤めから「金」恐怖症になって、山の中の村に移住してきた
ダメ~な感じの勘違い男を主人公にして、
農村という名の小宇宙で繰り広げられるスラップスティック。
ロハスとかスローライフとか言うのとはぜんぜん違う地平で、
都会を出て農村で暮らすとか、お金を使わず暮らすとか、
そういうことにどういう意味と手触りがあるのか。
そもそも、人が生きる、暮らすことにどういう意味があるのか。
ありえないようなシュールな村なのに、
どこかの地方にほんとうにありそうな、
すごく「場」としての力を持つ「かむろば村」でもって、
そうしたことをいろいろ深ーく感じさせる作品です。
非常に面白いです。
ああ、早く続きが読みたい。
2008年05月25日
生きる意味を教えてください
●生きる意味を教えてください――命をめぐる対話
田口ランディ
バジリコ株式会社 本体1600円+税
2008年3月14日初版第一刷発行
「ドラマで泣いて人生充実するのか、おまえ。」と同時期に
アマゾンで購入した同じ出版社の本。
対談集はどうしても途中で飽きて読みとおせないものも多いんだけど、
これは、非常に中身が濃く、いろんな角度から、
「生と死」について語られていて、面白かった。
発見がたくさんある本で、何度か読み返したくなる本だった。
対談に登場する人たちは以下のとおり
藤原新也、内田樹、西垣通、鷲田清一、竹内整一、
玄田有史、森達也、宮台真司、板橋興宗
田口ランディ
バジリコ株式会社 本体1600円+税
2008年3月14日初版第一刷発行
「ドラマで泣いて人生充実するのか、おまえ。」と同時期に
アマゾンで購入した同じ出版社の本。
対談集はどうしても途中で飽きて読みとおせないものも多いんだけど、
これは、非常に中身が濃く、いろんな角度から、
「生と死」について語られていて、面白かった。
発見がたくさんある本で、何度か読み返したくなる本だった。
対談に登場する人たちは以下のとおり
藤原新也、内田樹、西垣通、鷲田清一、竹内整一、
玄田有史、森達也、宮台真司、板橋興宗
2008年05月13日
ドラマで泣いて、人生充実するのか、おまえ。
●ドラマで泣いて、人生充実するのか、おまえ。
(深呼吸する言葉)著・きつかわゆきお/出版社・バジリコ
2008年3月23日 初版第一刷発行 1200円+税
新書版型のメッセージ集。
「ロックする思索者」きつかわゆきお(橘川幸夫)さんの本。
短く、鋭い、あるいは深い言葉が並んでます。
ほんとうに心に届く言葉(共鳴する言葉)は、
水に投げた石のように、自分の気持ちにさざ波を作る、
ということが実感できる本。
たとえば、
「壊れるものは作ったからだ。
生まれるものは壊れない。」
あるいは
「ロックとは、
表現欲求よりコミュニケーション欲求が、
勝っていること。」
など。
自分の状態によって響いてくる言葉が変わってくるのも面白い。
というわけで、このところの私の座右の書です。
深呼吸する言葉ネットワーク
きつかわさんのページ
そして、
私も深呼吸する言葉、始めてみました。
深呼吸する言葉・ながみねようこ
(深呼吸する言葉)著・きつかわゆきお/出版社・バジリコ
2008年3月23日 初版第一刷発行 1200円+税
新書版型のメッセージ集。
「ロックする思索者」きつかわゆきお(橘川幸夫)さんの本。
短く、鋭い、あるいは深い言葉が並んでます。
ほんとうに心に届く言葉(共鳴する言葉)は、
水に投げた石のように、自分の気持ちにさざ波を作る、
ということが実感できる本。
たとえば、
「壊れるものは作ったからだ。
生まれるものは壊れない。」
あるいは
「ロックとは、
表現欲求よりコミュニケーション欲求が、
勝っていること。」
など。
自分の状態によって響いてくる言葉が変わってくるのも面白い。
というわけで、このところの私の座右の書です。
深呼吸する言葉ネットワーク
きつかわさんのページ
そして、
私も深呼吸する言葉、始めてみました。
深呼吸する言葉・ながみねようこ
2008年04月14日
すっかりごぶさたです…
読書記録を…と思って書き出したブログですが、
なんだか忙しくなってくると、ぜんぜん更新する余力がなくなってました。
記録なので書名とか値段とかちゃんといろいろ書こうとすると、
なかなか書けなくなるんだよなー。
手元にあるもので、最近読んだもん、以下のとおり(順不同)。
○「ハチワンダイバー」1~6 柴田ヨクサル
…「このマンガがすごい2008」で、1位だったやつ。
去年の1位の」「デトロイトメタル~」にぜんぜんハマれなかったので、
どうかなあ、と思いつつ、やっと読んでみたら、これがまあ、面白かった。
羽海野チカもオビで絶賛してほんとに、ネーム(セリフ)のパワーがすごい。
ついつい一気読みしました。
○「7SEEDS」11 田村由美
゛…人類滅亡後のSFサバイバル群像劇の11巻目。
またもう、すごいことになってました。
マークの最期に思わず落涙。
マンガで久々に号泣。
物語がどう展開するのか、ある意味「LOST」より気になるかも。
○「スカイウォーカー」いくえみ綾
…ヤンサンに載ってた奥田民生とコラボ!の作品集。
けっこうよかった。
が、やっぱ今いくえみ綾は「潔く柔く」が傑作。
○「3月のライオン」1 羽海野チカ
…「ハチクロ」以降待望の新作。
ヤングアニマルでちょこちょこ読んでたときは
どうなんだろうか…と思ってたんだけど、
まとめて読むと、やっぱり、さすがだなあと思わせる描写力。
これも「ハチワン」と同じく、将棋のマンガなんだよなあ。
ええと、時間切れにつき本日はここまで。
(マンガばっかだなあ。)
感想にも解説にもイマイチなってないですが、
覚書ってことで、御免。
なんだか忙しくなってくると、ぜんぜん更新する余力がなくなってました。
記録なので書名とか値段とかちゃんといろいろ書こうとすると、
なかなか書けなくなるんだよなー。
手元にあるもので、最近読んだもん、以下のとおり(順不同)。
○「ハチワンダイバー」1~6 柴田ヨクサル
…「このマンガがすごい2008」で、1位だったやつ。
去年の1位の」「デトロイトメタル~」にぜんぜんハマれなかったので、
どうかなあ、と思いつつ、やっと読んでみたら、これがまあ、面白かった。
羽海野チカもオビで絶賛してほんとに、ネーム(セリフ)のパワーがすごい。
ついつい一気読みしました。
○「7SEEDS」11 田村由美
゛…人類滅亡後のSFサバイバル群像劇の11巻目。
またもう、すごいことになってました。
マークの最期に思わず落涙。
マンガで久々に号泣。
物語がどう展開するのか、ある意味「LOST」より気になるかも。
○「スカイウォーカー」いくえみ綾
…ヤンサンに載ってた奥田民生とコラボ!の作品集。
けっこうよかった。
が、やっぱ今いくえみ綾は「潔く柔く」が傑作。
○「3月のライオン」1 羽海野チカ
…「ハチクロ」以降待望の新作。
ヤングアニマルでちょこちょこ読んでたときは
どうなんだろうか…と思ってたんだけど、
まとめて読むと、やっぱり、さすがだなあと思わせる描写力。
これも「ハチワン」と同じく、将棋のマンガなんだよなあ。
ええと、時間切れにつき本日はここまで。
(マンガばっかだなあ。)
感想にも解説にもイマイチなってないですが、
覚書ってことで、御免。
タグ :マンガ
Posted by ながみねようこ at
17:13
│Comments(2)
2008年03月03日
ワンちゃん
●ワンちゃん
楊逸(ヤンイー) 文藝春秋 本体1143円
(2008年1月10日 第一刷発行)
これも芥川賞候補になった作品。
審査員講評で話題になっていて、
気になっていたので、単行本で買ってみた。
中国人が書いた日本語の文学。
なので、視点のズレ、意識のズレがナマっぽくて面白い。
でも、小説としてちゃんと読ませる面白味もある。
なんだか今まで読んだことない感覚の小説でした。
しかしまあ、中国の人たちって大変なことになってるなあ……。
芥川賞候補作以外の書き下ろし「老処女」っていうのも
身もフタもなくて面白かったです。
楊逸(ヤンイー) 文藝春秋 本体1143円
(2008年1月10日 第一刷発行)
これも芥川賞候補になった作品。
審査員講評で話題になっていて、
気になっていたので、単行本で買ってみた。
中国人が書いた日本語の文学。
なので、視点のズレ、意識のズレがナマっぽくて面白い。
でも、小説としてちゃんと読ませる面白味もある。
なんだか今まで読んだことない感覚の小説でした。
しかしまあ、中国の人たちって大変なことになってるなあ……。
芥川賞候補作以外の書き下ろし「老処女」っていうのも
身もフタもなくて面白かったです。
2008年03月03日
乳と卵(月刊文藝春秋)
●乳と卵
川上未映子
(でしたっけ? 手元に本がないので表記違ってたらスミマセン)
で、ここんとこ読んだもんを他にもまとめて。
これは、そろそろ単行本にもなったらしいけど、
単行本ではなくて、
文藝春秋の「芥川賞全文掲載、審査員講評つき」
という号を買って読みました。
(興味の持てそうな芥川賞のときだけしか買わない分厚い文藝春秋)
面白かった。
私としてはけっこう好きな小説。
前半はちょっとだるいなあ、と思ってたんだけど、
ラストはそれを補ってあまりある面白さ。
文体が独特だということは各所で言われているけど、
たしかに、なんというか、ジャズのようなうねりとリズムのある文体。
なので、乗れるまでが退屈、というのはあるんだろうな。
とても質感とか匂い、温度がある文章。
これからの作品も楽しみ。
それにしても、審査員講評のところで
石原慎太郎がものすごくムキになって
「おれはこんな作品認めない、ぜんぜんダメだ」
というようなことを言ってて、「へー」と思いました。
もはや、この人に好かれないほうが
小説としては面白いんじゃないかなあ、
と思います。
まあ、そういう人が審査員なのもどうなのか?と思うけど。
川上未映子
(でしたっけ? 手元に本がないので表記違ってたらスミマセン)
で、ここんとこ読んだもんを他にもまとめて。
これは、そろそろ単行本にもなったらしいけど、
単行本ではなくて、
文藝春秋の「芥川賞全文掲載、審査員講評つき」
という号を買って読みました。
(興味の持てそうな芥川賞のときだけしか買わない分厚い文藝春秋)
面白かった。
私としてはけっこう好きな小説。
前半はちょっとだるいなあ、と思ってたんだけど、
ラストはそれを補ってあまりある面白さ。
文体が独特だということは各所で言われているけど、
たしかに、なんというか、ジャズのようなうねりとリズムのある文体。
なので、乗れるまでが退屈、というのはあるんだろうな。
とても質感とか匂い、温度がある文章。
これからの作品も楽しみ。
それにしても、審査員講評のところで
石原慎太郎がものすごくムキになって
「おれはこんな作品認めない、ぜんぜんダメだ」
というようなことを言ってて、「へー」と思いました。
もはや、この人に好かれないほうが
小説としては面白いんじゃないかなあ、
と思います。
まあ、そういう人が審査員なのもどうなのか?と思うけど。
2008年03月03日
光の指で触れよ
●光の指で触れよ
池澤夏樹 中央公論社 本体2200円
(2008年1月25日 初版発行)
で、こちらが新刊。
前作同様500ページ以上に亙る長編なんだけど、
これも、するするーっと、あっという間に読めてしまった。
子どもにもめぐまれ、深く理解しあい、
絆を作っていた(ように見えた)
前作の主人公夫婦が、
夫に恋人ができたことで離れ離れになって……
というところから始まるのが今回の話。
帯にも「現代に生きる困難」というフレーズが書かれてるけど、
前作以上に、そういうことに深く向き合い、
丁寧に書かれている、という印象の話。
夫婦と家族の間の緊張感が話の中の軸になっているので、
「で、どうなるの? どうするの?」と興味を引かれているうちに
いろいろな問題やテーマも含めて一気に読ませる。
いい小説でした。
みんなが(自分も含め)こういうふうに生きたらいい、
と思える終わり方だったのもよかったっす。
池澤夏樹 中央公論社 本体2200円
(2008年1月25日 初版発行)
で、こちらが新刊。
前作同様500ページ以上に亙る長編なんだけど、
これも、するするーっと、あっという間に読めてしまった。
子どもにもめぐまれ、深く理解しあい、
絆を作っていた(ように見えた)
前作の主人公夫婦が、
夫に恋人ができたことで離れ離れになって……
というところから始まるのが今回の話。
帯にも「現代に生きる困難」というフレーズが書かれてるけど、
前作以上に、そういうことに深く向き合い、
丁寧に書かれている、という印象の話。
夫婦と家族の間の緊張感が話の中の軸になっているので、
「で、どうなるの? どうするの?」と興味を引かれているうちに
いろいろな問題やテーマも含めて一気に読ませる。
いい小説でした。
みんなが(自分も含め)こういうふうに生きたらいい、
と思える終わり方だったのもよかったっす。
タグ :池澤夏樹
2008年03月03日
すばらしい新世界
●すばらしい新世界
池澤夏樹 中央公論新社
(2000年9月10日初版発行)
8年前に刊行された池澤夏樹の長編小説。
読売新聞に1999年に連載されたもの。
この続編の小説が新刊で発表されたのだけど、
(「光の指で触れよ」という小説)
その前置きになるこちらのほうを読んでなかったので、
まず読んでみた。
面白かったですよ。
人と人の関係性、
電力をはじめとする現代の文化と人のつきあいかた、
考え方、
宗教のこと、
そういう大きなことが非常に示唆にとんだ言葉で書かれつつ、
登場人物のキャラクター設定が絶妙なので、
するするーっと読めてしまいました。
冒険小説的な側面もあるし、
家族小説でもある。
小説の中の考えに、私はとても共感しました。
池澤夏樹 中央公論新社
(2000年9月10日初版発行)
8年前に刊行された池澤夏樹の長編小説。
読売新聞に1999年に連載されたもの。
この続編の小説が新刊で発表されたのだけど、
(「光の指で触れよ」という小説)
その前置きになるこちらのほうを読んでなかったので、
まず読んでみた。
面白かったですよ。
人と人の関係性、
電力をはじめとする現代の文化と人のつきあいかた、
考え方、
宗教のこと、
そういう大きなことが非常に示唆にとんだ言葉で書かれつつ、
登場人物のキャラクター設定が絶妙なので、
するするーっと読めてしまいました。
冒険小説的な側面もあるし、
家族小説でもある。
小説の中の考えに、私はとても共感しました。
2008年02月14日
犬身
●犬身(kensin)
松浦理英子 朝日新聞社 本体2000円
(2007年10月30日発行)
すいぶん更新ごぶさたでした。
いやもうなにしろ引越しのごたごた&締め切りで……。
で、その合間を縫って読んだ長編がこれ。
けっこう一気に読んでしまいました。
ものすごーく後味のよくないものを、
痛快に描いた、力のある小説。
「人が犬になる」というありえない話を、
ありえるようにぐいぐい読ませる。
あと、登場人物(主人公が飼われる(!)女性の兄)の
ものすごい嫌なヤツぶりに、
「なんでここまで厭なのか……」といろいろ考えさせられる、
という部分でも、秀逸な仕組みがありました。
松浦理英子 朝日新聞社 本体2000円
(2007年10月30日発行)
すいぶん更新ごぶさたでした。
いやもうなにしろ引越しのごたごた&締め切りで……。
で、その合間を縫って読んだ長編がこれ。
けっこう一気に読んでしまいました。
ものすごーく後味のよくないものを、
痛快に描いた、力のある小説。
「人が犬になる」というありえない話を、
ありえるようにぐいぐい読ませる。
あと、登場人物(主人公が飼われる(!)女性の兄)の
ものすごい嫌なヤツぶりに、
「なんでここまで厭なのか……」といろいろ考えさせられる、
という部分でも、秀逸な仕組みがありました。
タグ :松浦理英子